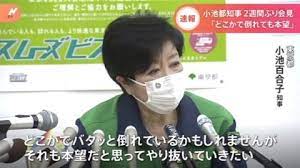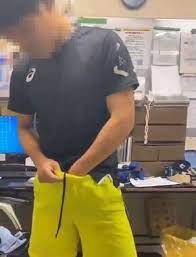改正国民投票法が成立 憲法改正に一歩前進
改正国民投票法が成立 改憲手続きを整備
配信


国会議事堂
憲法改正手続きに関する改正国民投票法は11日の参院本会議で、自民党や立憲民主党などの賛成多数により可決、成立した。
改憲の是非を問う国民投票の利便性を向上させるため、駅や商業施設でも投票できる「共通投票所」の導入など公選法に規定済みの7項目を新設する内容。
国民投票運動の際の政党スポットCMやインターネット広告の規制を巡り、施行後3年をめどに必要な措置を講じる旨の付則も盛り込まれた。
2018年の提出から8国会にわたって継続審議となっていたが、今国会で与野党が付則を加える修正で合意した。
【共同通信記事】
参照元/続きはこちら→ヤフーニュース
URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/aaa2641636731cd5ad75eb82dcc6bd4c8d1bca4b
何処でも投票可能。これは正に投票の可能性拡大・投票率アップに繋がる施策で良しだが、果たして二重投票、身替り投票等々の不正問題に対してはどうするつもりなのか?我が国の法は尽く犯罪者側を向いて居り、被害者側は何時も泣き寝入りに置かれているにも関わらず一切改正しようとはしない。何事も作る事は良い事だが、本当に悪いものへの罰則が甘いのが難点。これらについても同じ様に改正して欲しいと思います。
大事なのは投票しやすい場所の拡大がキーマン。
商業施設や公共の場所でも人は多いはずです。
だから国民は政策の決定権の最高峰ですから投票率が上がることを期待したい。
長かった。右、左はともかく、時代が移り変わるのに何十年も同じ憲法を維持し続けるのは異常なことだと思う。現代にそぐわない処は議論し、勇気をもって変えたい。人任せではなく、これは国民の義務だと思う。
9条だけにすごく焦点が当たって確かにそこは世の中二分されるけど、他の条文含めて本当にどこもいじらなくて良いのかってことをもっと右左関係なく考えた方が良いんじゃない?
こういう法律はどんどん進めて、国会議員の歳費や身分に関する法律はなぜ通さないんだろうね。言い訳ばかりして時間稼ぎをしてる感じ。そのうちうやむやになる。二階はここに来てもなお、カワイ夫妻を守ろうとしてる感じ。国民の払った税金の使い道に関することなのに。議院内閣制の国だけど、首相を国民がリコールできる制度にしてほしい。世論は無視されるからね。
憲法が政党に流されて決まるのは避けてもらいたい。
返信13
それから国民が直接政治や国の行く末に関わることが出来るようになるならば、学校でも政治について学ぶべきだよ。ダンスを必修科目にしてて大丈夫なのか?と思ってしまう。改憲手続きと同時に教育課程の見直しも望みます。
現状のようにマスコミの世論誘導、印象操作に右往左往されないように我々も勉強しないとね。
自民党と幹事長合意していた経緯からして、
成立は当然のことだと思う。
付則にある、広告やCM規制は重要なことである。
日本人の国民性からして、
目にはいる媒体による宣伝効果は絶大である。
憲法の改正の可否まで、
お金で左右されては行けない。
侵略戦争をしないのは当たり前ですが、国を、国土を、国民を、そして家族を守れるような憲法に早くしていきたいですね。
とっても怖い事だよこれは。
海外からのお金で【誰かが勝手に】どれだけネット上にCMを流してもなんの縛りもないんだから。
韓流スターを大規模に動員してCMを作って流したら、おばさん連中は結構騙される人もいると思うし、最近の男女の若手アイドルを使ったら若年層にも結構な影響がある。
自民党の中枢はいま親中韓だし、とんでもない方向に改憲されないことをただ祈るしかない。「国境線・離島は相手国と相談して決める」なんて内容なら、誤魔化されないだろうけど、うまーく国民をだますような言い回しの改憲案だったら、下手するとCM攻勢でひっくり返っちゃうよ。
各条文ごとに個別に判断できないのであれば、改憲する意味がないと思う。
しかし、改憲が目的になってはいけません。憲法は最高法規で「国家権力から国民を守る」ために存在します。不正だらけ、上級国民や権力者に都合良く作られては、本当に日本は滅びます。それだけ、憲法改正は日本の未来を左右します。
国民は、改憲内容を理解し、監視しなければなりません。
可決された後、国民が首を捻ったり批判が多くなる改正にならないように。
自分も含めてだけど、私念に絡め取られず情報を取捨選択して正しい判断力を身につけないと、あとで大変なことになってしまう。盲信は思考停止と同じだ。
国民一人一人が政治に積極的に関わって勉強していくことが今後大事ですね。
とりあえず試しに「NHKの存続の可否」を国民投票してみてはいかがでしょうか?生活に密着しているので投票率も高く、社会実験にぴったりかと思います。
日本の未来を危うくしない様、マスコミに踊らされずに注視して考えないといけない。
無関心、政治家任せは危険だと思う。
というところがミソ。各議員という事は、衆参議院それぞれで、それぞれ3分の2以上の賛成が必要という事。仮に衆議院で満場一致で可決されたとして、参議院にいって3分の1の80名やそこらの反対で否決となる。これはかなり高いハードルとなる。
両議院の総議員の3分の2以上にしないと。
それと、国民投票で過半数となると、例えば20%程度の投票率でも10%超の賛成票が入ればよいことになる。これで国民の声が反映されたと言えるか?
過半数且つ、全有権者の30%以上の賛成くらいにしないと。
第4条で衆議院議員は465人、参議院議員は248人です
議員定位数を大幅に削減、できれば半分くらいにして
議員報酬と議員年金の削減にも手を付けるべきですね
そして事件を起こした場合には懲戒免職で報酬は国庫への返還。
こんな感じで国会議員にも負担を強いるべき。
ついに成立しましたか。実施する側は運用には十分注意して欲しいものです。国会で成立しなかった憲法改正案について国民投票での決着を図った場合、僅差での改正やまたは非改正となるでしょうが、これが国民の分断を招く可能性があることを憂慮します。例えば、51%の人が賛成としても、49%の人が反対のことを本当に成立させて良いのでしょうか。国民投票に至るまでのお互いの理解を深めるような努力が必要と思います。また、一括法案のようなことを避けることも重要かと。プーチンさんはそれで、大統領任期の延長を紛れ込ませたという前例もありますので。
改憲が可能になることは、問題はこれからであり、その最大の焦点は改憲される内容にある。そして肝心である国民が求める内容として改憲されるのか。内閣が主権を握る今の時代を、三権が主権になる平時に戻すべきである。一過性のものであるはずの疫病に惑わされ見るべき方向を見失ってはいけない。これから出されるであろう改憲内容案を必ず確認して投票をする必要がある。
国民ももっと憲法に対する関心を深めるべきです。
よく、「改憲派」「護憲派」などといいますが、「護憲」という言葉は、実に奇妙な言葉です。
「憲法を改正しない」=「憲法を守る、護憲」という意味で使われているようですが、実にナンセンスですね。
憲法そのものが、改正手続きを定めているという事は、改憲も想定しているという事です。
なぜ改憲しないことが憲法を守ることになるのか、理解不能です。
憲法を絶対に改正してはならないとしたら、「不磨の大典」と呼ばれた大日本帝国憲法と同じではないでしょうか。
付則のCM規制と外国人寄付規制については3年を目処にとは言わず、速やかに検討して欲しい。
それと改憲に関しては一括でなく、各章項毎(条項毎がより望ましい)にして欲しいけどね。何度も投票しなきゃいけないのは面倒だろうけど、一括だとここは賛成だけどこっちは反対って事が絶対ある。で、決められないから投票しないとか。
そもそも憲法ってとっつきにくいし分からないって人が多いでしょ。だから条項毎なら情報も得やすいし分かり易いでしょ。自分に影響するなら尚更。
投票率上げるなら投票場所や環境も大事だけど、そもそも興味を持って貰わない事には話にならないと思うんだよね。
でも、あれか、国としてはよく分かった上で投票されると困ったりするんだろうね。
返信0
最終案がどこぞにも乗っていないのでどうなったのかが心配だ
併せて常に考えて欲しいのは、未来の事。
本当に未来の日本国民に胸を張れる憲法改正と言えるのか?ということ。
議員削減の話はどこにいった?自分たちには甘く、国民には、お願いばかり、、、国民は次の選挙で怒りをぶつけるべきだ!
報道って意味あるのかな?って思うことがある
でもそうしないと、情報流してくれなくなるんだろうね
ほんと、報道って意味あるのかなぁ?政府が発表するだけで良くね?
改正国民投票法が成立したので次に移ろう。憲法改正、つまり9条を改正しないと国が守れないという人たちがいる。左右のイデオロギーは横に置いておいて、実務的・現実的にどうなのか。急速に軍事力を拡大し、海外侵出を始めている隣国の脅威に対抗するのに、自衛隊法等の関連法を改正すれば間に合うのか、9条等の憲法を改正する必要があるのか、国民全体で話をして考える必要がある。
今のご時世、ネットで投票可能にして貰えれば、
場所の管理も煩雑じゃなく、時間を気にしないで投票出来る。
そもそも、投票率が上がらないのは国民に寄り添った政策をしてくれない政治側の問題では?
個人としては、期日前投票で毎回投票してるし、
意思があれば、投票に行く時間と機会を設けるハズ。
もう「興味ない」では済まされなくなりました。
国民も勉強が必要です。
「興味ない」や「不投票」は白紙委任。
改悪されても後から文句は言えませんよ。
「投票で信任を得た」ことになるんだから。
「社会ニュース」カテゴリーの関連記事